ORACLE WITH AS 用法
原文传送门:http://blog.csdn.net/wh62592855/archive/2009/11/06/4776631.aspx 记得以前在论坛里看到inthirties用到过WITH AS这个字眼,当时没特别在意。今天在一个帖子里又看到有人用这个,所以就去网上搜了搜相关内容,自己小试了一把,写下来,方便以后
原文传送门:http://blog.csdn.net/wh62592855/archive/2009/11/06/4776631.aspx
记得以前在论坛里看到inthirties用到过WITH AS这个字眼,当时没特别在意。今天在一个帖子里又看到有人用这个,所以就去网上搜了搜相关内容,自己小试了一把,写下来,方便以后忘了的话学习。
===================================================================================
先举个例子吧:
有两张表,分别为A、B,求得一个字段的值先在表A中寻找,如果A表中存在数据,则输出A表的值;如果A表中不存在,则在B表中寻找,若B表中有相应记录,则输出B表的值;如果B表中也不存在,则输出"no records”字符串。
再举个简单的例子
with a as (select * from test)
select * from a;
其实就是把一大堆重复用到的SQL语句放在with as 里面,取一个别名,后面的查询就可以用它
这样对于大批量的SQL语句起到一个优化的作用,而且清楚明了
下面是搜索到的英文文档资料
About Oracle WITH clause
Starting in Oracle9i release 2 we see an incorporation of the SQL-99 “WITH clause”, a tool for materializing subqueries to save Oracle from having to re-compute them multiple times.
The SQL “WITH clause” is very similar to the use of Global temporary tables (GTT), a technique that is often used to improve query speed for complex subqueries. Here are some important notes about the Oracle “WITH clause”:
• The SQL “WITH clause” only works on Oracle 9i release 2 and beyond.
• Formally, the “WITH clause” is called subquery factoring
• The SQL “WITH clause” is used when a subquery is executed multiple times
• Also useful for recursive queries (SQL-99, but not Oracle SQL)
To keep it simple, the following example only references the aggregations once, where the SQL “WITH clause” is normally used when an aggregation is referenced multiple times in a query.
We can also use the SQL-99 “WITH clause” instead of temporary tables. The Oracle SQL “WITH clause” will compute the aggregation once, give it a name, and allow us to reference it (maybe multiple times), later in the query.
The SQL-99 “WITH clause” is very confusing at first because the SQL statement does not begin with the word SELECT. Instead, we use the “WITH clause” to start our SQL query, defining the aggregations, which can then be named in the main query as if they were “real” tables:
WITH
subquery_name
AS
(the aggregation SQL statement)
SELECT
(query naming subquery_name);
Retuning to our oversimplified example, let’s replace the temporary tables with the SQL “WITH clause”:
WITH
sum_sales AS
select /*+ materialize */
sum(quantity) all_sales from stores
number_stores AS
select /*+ materialize */
count(*) nbr_stores from stores
sales_by_store AS
select /*+ materialize */
store_name, sum(quantity) store_sales from
store natural join sales
SELECT
store_name
FROM
store,
sum_sales,
number_stores,
sales_by_store
where
store_sales > (all_sales / nbr_stores)
;
Note the use of the Oracle undocumented “materialize” hint in the “WITH clause”. The Oracle materialize hint is used to ensure that the Oracle cost-based optimizer materializes the temporary tables that are created inside the “WITH” clause. This is not necessary in Oracle10g, but it helps ensure that the tables are only created one time.
It should be noted that the “WITH clause” does not yet fully-functional within Oracle SQL and it does not yet support the use of “WITH clause” replacement for “CONNECT BY” when performing recursive queries.
To see how the “WITH clause” is used in ANSI SQL-99 syntax, here is an excerpt from Jonathan Gennick’s great work “Understanding the WITH Clause” showing the use of the SQL-99 “WITH clause” to traverse a recursive bill-of-materials hierarchy
The SQL-99 “WITH clause” is very confusing at first because the SQL statement does not begin with the word SELECT. Instead, we use the “WITH clause” to start our SQL query, defining the aggregations, which can then be named in the main query as if they were “real” tables:
WITH
subquery_name
AS
(the aggregation SQL statement)
SELECT
(query naming subquery_name);
Retuning to our oversimplified example, let’s replace the temporary tables with the SQL “WITH” clause”:
=================================================================================
下面自己小试一把,当然,一点都不复杂,很简单很简单的例子,呵呵。
好了就先记这些吧,以后看到了新的用法再补充。

ホットAIツール

Undresser.AI Undress
リアルなヌード写真を作成する AI 搭載アプリ

AI Clothes Remover
写真から衣服を削除するオンライン AI ツール。

Undress AI Tool
脱衣画像を無料で

Clothoff.io
AI衣類リムーバー

AI Hentai Generator
AIヘンタイを無料で生成します。

人気の記事

ホットツール

メモ帳++7.3.1
使いやすく無料のコードエディター

SublimeText3 中国語版
中国語版、とても使いやすい

ゼンドスタジオ 13.0.1
強力な PHP 統合開発環境

ドリームウィーバー CS6
ビジュアル Web 開発ツール

SublimeText3 Mac版
神レベルのコード編集ソフト(SublimeText3)

ホットトピック
 7455
7455
 15
15
 1375
1375
 52
52
 77
77
 11
11
 14
14
 9
9
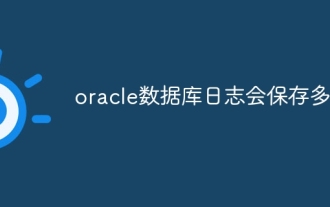 Oracle データベースのログはどのくらいの期間保存されますか?
May 10, 2024 am 03:27 AM
Oracle データベースのログはどのくらいの期間保存されますか?
May 10, 2024 am 03:27 AM
Oracle データベース ログの保存期間は、次のようなログのタイプと構成によって異なります。 REDO ログ: 「LOG_ARCHIVE_DEST」パラメータで構成された最大サイズによって決定されます。アーカイブ REDO ログ: 「DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE」パラメータで構成された最大サイズによって決まります。オンライン REDO ログ: アーカイブされず、データベースの再起動時に失われます。保持期間はインスタンスの実行時間と一致します。監査ログ: 「AUDIT_TRAIL」パラメータによって構成され、デフォルトで 30 日間保持されます。
 Oracle にはどれくらいのメモリが必要ですか?
May 10, 2024 am 04:12 AM
Oracle にはどれくらいのメモリが必要ですか?
May 10, 2024 am 04:12 AM
Oracle が必要とするメモリーの量は、データベースのサイズ、アクティビティー・レベル、および必要なパフォーマンス・レベル (データ・バッファー、索引バッファーの保管、SQL ステートメントの実行、およびデータ・ディクショナリー・キャッシュの管理) によって異なります。正確な量は、データベースのサイズ、アクティビティ レベル、および必要なパフォーマンス レベルによって影響されます。ベスト プラクティスには、適切な SGA サイズの設定、SGA コンポーネントのサイズ設定、AMM の使用、メモリ使用量の監視などが含まれます。
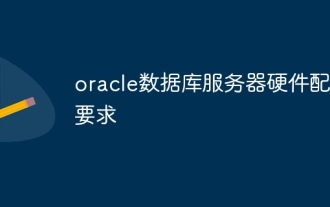 Oracle データベース サーバーのハードウェア構成要件
May 10, 2024 am 04:00 AM
Oracle データベース サーバーのハードウェア構成要件
May 10, 2024 am 04:00 AM
Oracle データベース サーバーのハードウェア構成要件: プロセッサ: マルチコア、少なくとも 2.5 GHz のメイン周波数 大規模なデータベースの場合は、32 コア以上が推奨されます。メモリ: 小規模データベースの場合は少なくとも 8 GB、中規模のデータベースの場合は 16 ~ 64 GB、大規模なデータベースまたは重いワークロードの場合は最大 512 GB 以上。ストレージ: SSD または NVMe ディスク、冗長性とパフォーマンスのための RAID アレイ。ネットワーク: 高速ネットワーク (10GbE 以上)、専用ネットワーク カード、低遅延ネットワーク。その他: 安定した電源、冗長コンポーネント、互換性のあるオペレーティング システムとソフトウェア、放熱と冷却システム。
 Oracle データベースを使用するために必要なメモリの量
May 10, 2024 am 03:42 AM
Oracle データベースを使用するために必要なメモリの量
May 10, 2024 am 03:42 AM
Oracle データベースに必要なメモリの量は、データベースのサイズ、ワークロードの種類、同時ユーザーの数によって異なります。一般的な推奨事項: 小規模データベース: 16 ~ 32 GB、中規模データベース: 32 ~ 64 GB、大規模データベース: 64 GB 以上。考慮すべきその他の要素には、データベースのバージョン、メモリ最適化オプション、仮想化、ベスト プラクティス (メモリ使用量の監視、割り当ての調整) などがあります。
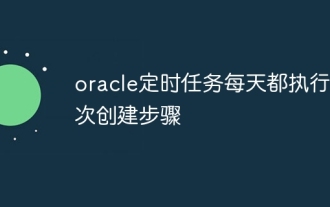 Oracle のスケジュールされたタスクは、作成ステップを 1 日に 1 回実行します。
May 10, 2024 am 03:03 AM
Oracle のスケジュールされたタスクは、作成ステップを 1 日に 1 回実行します。
May 10, 2024 am 03:03 AM
Oracle で 1 日に 1 回実行されるスケジュールされたタスクを作成するには、次の 3 つの手順を実行する必要があります。 ジョブを作成します。ジョブにサブジョブを追加し、そのスケジュール式を「INTERVAL 1 DAY」に設定します。ジョブを有効にします。
 Oracle データベースにはどれくらいのメモリが必要ですか?
May 10, 2024 am 02:09 AM
Oracle データベースにはどれくらいのメモリが必要ですか?
May 10, 2024 am 02:09 AM
Oracle Databaseのメモリー要件は、データベースのサイズ、アクティブ・ユーザーの数、同時問合せ、有効な機能、およびシステム・ハードウェア構成の要素によって異なります。メモリ要件を決定する手順には、データベース サイズの決定、アクティブ ユーザー数の推定、同時クエリの理解、有効な機能の検討、システム ハードウェア構成の調査が含まれます。
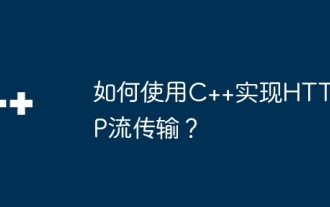 C++ を使用して HTTP ストリーミングを実装するにはどうすればよいですか?
May 31, 2024 am 11:06 AM
C++ を使用して HTTP ストリーミングを実装するにはどうすればよいですか?
May 31, 2024 am 11:06 AM
C++ で HTTP ストリーミングを実装するにはどうすればよいですか? Boost.Asio と asiohttps クライアント ライブラリを使用して、SSL ストリーム ソケットを作成します。サーバーに接続し、HTTP リクエストを送信します。 HTTP 応答ヘッダーを受信して出力します。 HTTP 応答本文を受信して出力します。
 Oracleでリスニングプログラムを開始する方法
May 10, 2024 am 03:12 AM
Oracleでリスニングプログラムを開始する方法
May 10, 2024 am 03:12 AM
Oracle リスナーは、クライアント接続リクエストを管理するために使用されます。起動手順は次のとおりです。 Oracle インスタンスにログインします。リスナー構成を見つけます。 lsnrctl start コマンドを使用してリスナーを開始します。 lsnrctl status コマンドを使用して起動を確認します。




